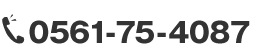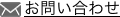今日、NETで購入した地下足袋が届きました。
製品サイズは26.0cmでしたが、私の足の26.5cmでもコハゼを調整すれば何とか入る大きさです。
足の裏側にはゴムのソールが張ってありますから、滑りやすい場所でも安心して登ることが出来そうです。また、つま先も黒いゴムで覆われていますから、何か尖ったようなものが当たっても怪我をするようなことはないですね。
足場を登ったりする際には、スポーツシューズを履いていましたが、勾配が強い屋根だと滑りそうで少し不安な感じもありました。うちのペンキ屋さんの親方が、いつも地下足袋で足場を登っていくのを見て、外周りで作業をするなら、地下足袋もありかなとずっと思っていました。
地下足袋と聞くと、古い人だと土木作業員を思い出すかも知れませんが、今はウォーキングや登山といった用途に利用する人や外国人の購入も多いらしいです。昔の日本人は、便利なものを考え出したと思います。
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。
※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。